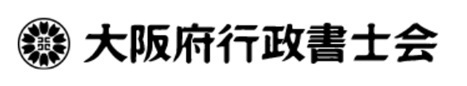メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
永住許可の再申請
永住許可の再申請について【行政書士が詳しく解説】

永住許可の再申請とは?
一度永住許可申請を行ったものの、「不許可通知」を受け取ってしまう方は少なくありません。
特に2019年に「永住許可に関するガイドライン」が改正されて以降、審査基準は以前よりも厳格化されています。
実際、2020年度の統計では、永住許可率は約50%とされており、申請者の半数が不許可となっているのが現状です。
不許可の通知を受けた方からは、「なぜ不許可になったのか分からない」と戸惑う声も多く寄せられます。
というのも、送付される「不許可通知書」には簡略な理由しか記載されておらず、具体的な改善点までは書かれていないからです。
そのため、不許可通知書を持参して入国管理局へ出向き、審査官から直接ヒアリングを受けることが第一ステップとなります。
再申請できるかどうかの判断が重要
また、不許可となったからといって、すぐに諦める必要はありません。再申請によって許可が得られるケースは数多く存在します。
以下のような原因であれば、比較的短期間でリカバリーが可能です。
・年収がわずかに基準を下回っていた
・課税証明書や納税証明書に記載漏れがあった
・軽微な交通違反があった
これらは書類の見直しや補足説明を加えることで、再審査で許可が下りる可能性があります。
一方で、
・虚偽申告があった
・重大な在留違反(オーバーステイなど)があった
といった場合には、一定の期間を空けてからの再申請が必要になるなど、慎重な対応が求められます。
再申請に向けた準備と改善ポイント
再申請を成功させるためには、まず永住許可のガイドラインを再確認し、以下の3つの主要要件を再点検しましょう。
・生計の安定性(年収・納税状況)
・素行の良好性(違反歴・納付状況など)
・日本での継続的な在留期間(原則10年以上)
また、前回の申請と比較して、どの点が改善されたかを明確にし、その内容を理由書や補足資料に記載することが非常に重要です。
書類の整合性・説得力が再申請の成否を大きく左右します。
専門家(行政書士)に依頼するメリット
不許可となった永住申請を再チャレンジする際は、ビザ申請を専門とする行政書士に相談することで成功率が大きく向上します。
行政書士であれば、
・不許可理由に応じた再申請戦略の立案
・適切な補足資料や反論書の作成
・審査官とのヒアリング同席(必要に応じて)
など、プロの視点で総合的にサポートすることが可能です。
「次こそは絶対に許可を取りたい」とお考えの方は、専門家の力を借りることで、安心して申請準備を進められるでしょう。
再申請から永住許可を取得するまでの流れ
● 担当審査官から不許可理由の聴き取り
永住許可申請が不許可となった場合、最初にすべきことは、入国管理局の審査官に直接会い、不許可の具体的な理由を確認することです。
通常、送付される不許可通知書には「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号に適合しない」など、法的な根拠条文のみが記載されており、実際にどの点が問題であったのかについては一切触れられていません。
そのため、申請者自身が能動的に入国管理局を訪問し、審査官との個別面談(ヒアリング)を行う必要があります。
● ヒアリングは不許可通知受領から半年以内に
この聴き取り面談は、不許可通知を受け取ってから原則6か月以内であれば、常識の範囲内で何度でも実施が可能です。
面談に必要な持ち物は以下の通りです:
・不許可通知書
・在留カードやパスポートなどの本人確認書類
ただし、重要な注意点があります。入管審査官は、申請者から質問されない限り、自ら積極的に不許可理由を詳しく説明する義務はありません。
そのため、ただ訪問するだけでは実りのある聴き取りにはならず、事前準備が非常に重要です。
● 効果的な面談のために準備すべきポイント
面談を有意義なものにするためには、以下のような準備が欠かせません:
・永住許可の最新ガイドラインや審査運用の基準を把握しておく
・自分の申請のどの部分に問題があったか予測する
・どのように改善・再提出すれば許可が見込めるのかを具体的に質問する
特に重要なのは、
・「不許可となった具体的な原因」を明確にすること
・「再申請で許可を得るために必要な対策」を審査官から確認すること
この2点です。これらが不明確なまま再申請しても、また同じ理由で不許可になる可能性が高くなります。
● 専門家(行政書士)の同行で成功率アップ
ヒアリングは申請者ご自身で行うことも可能ですが、ビザ申請に強い行政書士に同行を依頼することで、より実りある面談が実現します。
・行政書士が審査官とのやり取りを適切にリード
・必要な情報を確実に引き出す質問設計が可能
・聞き逃しや誤解をその場で修正・補足できる
特に、「不許可理由に心当たりがない」「どうしても永住ビザを取得したい」という方にとっては、専門家のサポートは再申請の成功率を大きく左右する鍵になります。
当事務所でも、多くの永住不許可からの再申請を支援しており、適切な対策・書類修正・面談同行などを通じて許可を得た事例も多数ございます。まずはお気軽にご相談ください。
再申請でリカバリー可能な理由
永住許可申請が不許可になったとしても、その理由が明確に分かっており、必要な改善策を講じることができれば、再申請で許可を得る可能性は十分にあります。
とくに、書類の不備や説明不足といった手続き上の問題が原因だった場合には、リカバリーが可能な典型例です。
たとえば、必要な添付資料が一部不足していた場合や、理由書の記述が抽象的で審査官に誤解を与えたケースなどは、適切な書類を再提出したうえで、補足説明を丁寧に行うことで、申請の信頼性を大きく高めることができます。
また、再申請では、前回からどのような点を改善したのかを具体的に示すことが極めて重要です。
収入面での上昇や納税実績の追加、転職後の安定就労など、状況の変化を証拠とともに説明することが成功への鍵となります。
ただし、以前の申請内容と矛盾する説明や資料を提出してしまうと、「虚偽申請」と見なされてしまう可能性もあるため注意が必要です。
出入国在留管理庁は、過去の申請履歴や面談内容をすべて記録・保管しており、内容に一貫性がないと判断された場合には再申請が不利になることがあります。
そのため、過去の申請内容をしっかりと踏まえた上で、整合性を保ちながら説得力のある説明を用意することが重要です。
一度不許可になってしまったとしても、あきらめる必要はありません。専門家のサポートを受けながら、客観的な視点で改善点を洗い出し、万全の体制で再申請に臨めば、永住許可を得られる道はきっと開けます。
再申請でリカバリー不可能な理由
永住許可の再申請は、多くの場合において改善の余地がありますが、どうしてもリカバリーが難しいケースも存在します。
その典型的な例が、申請者本人または同時申請している家族が、そもそも永住許可の基本的な要件を満たしていない場合です。
たとえば、日本での居住年数が基準に足りていない、安定した収入がない、あるいは過去に重大な在留違反歴がある場合には、どれほど丁寧に準備を整えても許可を得るのは困難といえるでしょう。
中でも特に厳しく審査されるのが、税金・健康保険料・年金の納付状況です。
最近の審査傾向では、たとえ最終的に納付を済ませていたとしても、「期限内に支払っていたかどうか」が強く問われるようになっており、納期限を過ぎていたという理由だけで不許可になることも珍しくありません。
つまり、「納付したかどうか」ではなく、「きちんと期限を守っていたかどうか」が判断の分かれ目になります。
また、家族全員で永住申請を行う場合には、主申請者だけでなく、配偶者や子どもを含む全員の納税記録や年金の加入・納付状況まで審査の対象となります。
たとえ本人が要件を満たしていたとしても、家族の一人にでも未納や滞納があれば、そのことで全員の申請が不許可になるリスクがあるのです。
このように、永住許可の要件に本質的に届いていない場合は、再申請による短期的なリカバリーは現実的ではありません。
こうしたケースでは、必要な収入や納付実績を積み重ねる期間を確保し、数年後にあらためて要件を満たした上で再申請を行うことが現実的な対応策となります。
さらに、永住許可の審査基準や入管の運用方針は、年ごとに微妙に変更されることがあるため、申請のタイミングも慎重に見極める必要があります。
再申請を検討する際は、必ず最新のガイドラインや審査基準に目を通し、現行基準に自分が本当に適合しているかを確認することが不可欠です。
焦らずに着実に準備を重ね、確実に永住許可を得られるタイミングを見極めていくことが、成功への最短ルートとなるでしょう。
ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。全国オンライン対応で受付しております。
このページの監修者

代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号
全国の外国人ビザ申請・帰化申請手続きを中心に、年間許可数150件、99.2%の高許可率の実績があります。
「お客様の目線に立ち、最適かつ丁寧なサポートと確実な許可取得を心がけております。」
お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

| 営業時間 | 9:00~20:00 |
|---|
| 定休日 | なし(土日祝の対応可) |
|---|
メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)
お気軽にご相談下さい。
お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。